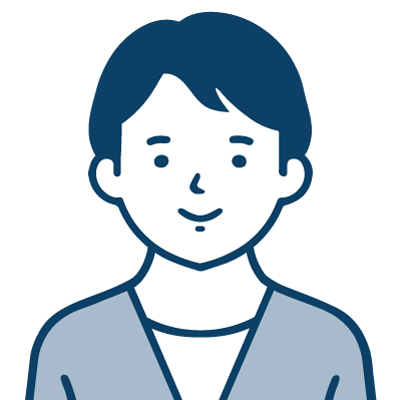金地金とは?
金地金(きんじがね)とは、資産保有や投資目的で取引される金の塊のことを指します。
通常は「インゴット」とも呼ばれ、一定の重さと純度(通常は純度99.99%のK24)を満たした金の現物資産です。
1g〜1kgまでさまざまなサイズがあり、個人で保有することも可能です。
ジュエリーや装飾品とは異なり、金地金には美的価値ではなく「金そのものの価値」が反映されており、市場価格に連動して日々価値が変動します。
資産分散の一環として注目されており、保有したまま贈与や相続、売却といった用途にも活用されています。
関連リンク:インゴットとは?購入方法や種類を解説
金地金贈与の方法
金地金贈与とは、家族や親族などに金の現物(インゴット)を無償で譲り渡す行為を指します。
贈与の方法としては「現物の金地金を手渡す」「贈与契約書を作成して記録を残す」などの手続きが基本です。
金地金は目に見える資産であるため、贈与が「成立している」と税務署が判断しやすく、申告義務の有無や贈与税の課税対象となるかどうかにも影響します。
実務上は、贈与を証明するために受贈者との間で「贈与契約書」を作成しておくのが望ましく、金地金の写真やシリアル番号、贈与日などを記載しておくと信頼性が高まります。
贈与額が年間110万円を超える場合は、原則として贈与税の申告が必要となるため、税理士への相談も視野に入れて進めると安心です。
金地金贈与のメリット・デメリットは?

メリット
金地金贈与には、以下のような複数のメリットがあります。
- 現物資産をそのまま渡せるため、現金化せずに資産移転ができる。
- 受贈者はローンや返済義務を負わず、受け取った金を自由に保有・売却できる。
- 金は世界基準で価格が決まり、流通性が高いため扱いやすい。
- インフレや通貨下落など、経済変動に対するリスクヘッジとなる。
- 金価格の上昇により、将来的に資産価値が高まる可能性がある。
- 紙幣や金融資産と比べて、長期保有に適している。
デメリット
一方で、金地金贈与にはいくつかの注意すべきデメリットも存在します。
もっとも大きなポイントは、贈与額によっては「贈与税」の課税対象となることです。
年間110万円を超える金額を贈与した場合、原則として受贈者が申告・納税の義務を負います。
事前に税制を理解していないと、後から税務署からの指摘を受けることもあるため注意が必要です。
また、贈与された金地金が本当に贈与されたものなのか、売買や貸与ではないかを明確にするための「証拠書類(贈与契約書)」の作成も重要です。
これが曖昧だと、贈与が認められなかったり、相続税の対象に切り替えられる可能性もあるため、形式面でも適切な手続きを踏むことが求められます。
贈与税の仕組みと注意点

贈与税の仕組みと規則
贈与税とは、個人から財産を無償でもらった際にかかる税金のことです。
1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額が「基礎控除額(年間110万円)」を超える場合、受贈者に贈与税の納税義務が発生します。
金地金贈与もこの対象に含まれ、相場に基づいた評価額で課税される点に注意が必要です。
申告は受贈者が翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があり、期限を過ぎると加算税や延滞税が発生することもあります。
正しく納税を行うためには、贈与契約書の作成や評価額の確認など、事前準備が重要です。
贈与税と相続税の違い
贈与税と相続税は、いずれも「財産の取得」に対して課税される税金ですが、発生のタイミングや計算方法に違いがあります。
贈与税は「生前」に財産を譲り受けたときに課税され、相続税は「死亡後」に財産を取得したときに課税されるものです。
贈与税の方が課税率が高めに設定されており、場合によっては相続した方が税負担が軽く済むこともあります。
ただし、生前に少しずつ財産を贈与することで、相続財産を減らして全体的な税負担を抑える「生前贈与」の活用も可能です。
贈与と相続、それぞれの仕組みを理解し、家族構成や資産状況に応じた選択をすることが大切です。
金地金贈与の際の注意点

贈与契約書を必ず作成する
金地金贈与では、実際に贈与が行われたことを証明するために、贈与契約書を作成しておくことが非常に重要です。
税務署から「これは本当に贈与なのか?」「贈与でなく預かっているだけでは?」と疑われた場合、贈与契約書がなければ認められない可能性があります。
契約書には、贈与日・贈与者と受贈者の氏名・金地金の量や特徴(重量・刻印・シリアル番号など)を明記しておくと安心です。
書面を残しておくことで、将来のトラブルや税務調査にも対応しやすくなります。
評価額の算出と課税対象の確認
金地金は日々相場が変動するため、贈与時の評価額を正確に把握する必要があります。
贈与税の申告においては、贈与した日の金相場を基準に金額を算出し、その評価額が110万円を超える場合は課税対象となります。
相場によっては少量の金でも申告が必要になるケースもあるため、贈与前に最新の相場を確認しておくことが大切です。
また、評価額を自己判断で見積もるのではなく、貴金属の取扱業者や税理士のアドバイスを受けることで、正確で適切な申告につながります。
誤った申告はペナルティの対象にもなるため注意が必要です。
贈与税対策と金活用のポイント

毎年少額ずつ分けて贈与する
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、これをうまく活用することで、税負担を抑えながら計画的に金地金を贈与することが可能です。
たとえば、1年に1回、110万円以内の評価額となる範囲で金を贈与すれば、非課税で資産を移転できます。
これを複数年にわたって繰り返す「暦年贈与」は、生前贈与の基本戦略として広く活用されています。
ただし、実態は贈与なのに書面がなかったり、渡す意思や管理が不明確な場合、税務署から「相続税回避目的」と判断されることもあるため、毎年しっかりと贈与契約書を交わし、記録を残しておくことが大切です。
相場を見て柔軟に活用する
金は日々価格が変動する資産であるため、相場が上昇傾向にあるときに贈与すると、将来的に受贈者にとって資産価値が大きくなる可能性があります。
一方で、相場が高すぎると課税対象となる評価額も上がるため、金額やタイミングには注意が必要です。
また、贈与に使わない金地金は、資産の一部として保有し続けることで、インフレヘッジや資産分散の役割も果たします。
現金や不動産とバランスをとりながら、金地金を柔軟に「贈与」と「保有」の両面で活用していくことが、賢い金活用のポイントです。
金地金と贈与税に関するよくある質問
金地金を売却すると確定申告が必要ですか?
はい、金地金を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、原則として確定申告が必要です。
個人が所有していた金を売却して得た利益は「譲渡所得」として課税対象となり、特別控除額(50万円)を超える部分に対して税金がかかります。
売却価格だけでなく、購入時の金額や保有期間によっても計算結果が変わるため、領収書や購入証明書は必ず保管しておきましょう。
なお、短期間の売買を繰り返している場合などは、事業所得と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
金地金贈与のデメリットはなんですか?
金地金贈与のデメリットとして最も注意したいのは、贈与額が110万円を超えると贈与税が課税される可能性があることです。
特に金の価格が上昇しているタイミングでは、少量でも評価額が高くなるため、思わぬ課税対象になることもあります。
また、贈与の事実を明確にするために贈与契約書を作成したり、申告手続きが必要になるなど、実務的な準備も求められます。
金は現物資産であるため、贈与後の保管や管理方法についても事前に受贈者とよく相談しておくことが重要です。